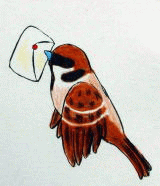
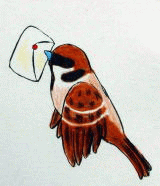
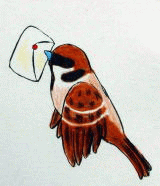 |
バンディング問題その後 | 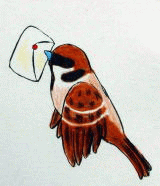 |
||
|---|---|---|---|---|
| はじめに | |||
|---|---|---|---|
|
山階鳥類研究所の標識研究室室長より回答書が出てから5ヶ月が過ぎました。 格調が高く、分かりにくい回答書に含まれているであろう、改善に対する心構え、優しい気持ちをくみ取り、期待して矛を収めたのですが。 |
|||
| それ以後、MAKIさんのバンディング見学と考え方について、標識研究室室長(以後、室長と表現させていただきます)からの修正意見等を見ていると、山階鳥類研究所(以後、山階と表現させていただきます)は、改善を進める気持ちがないのでは、と感じ始めています。 |
|||
|
1.回答についての全体的な姿勢 |
|||
|---|---|---|---|
| 佐藤さん、和田さんの質問に対して、山階の回答で共通している点は、問題点を認めて・改善しますと回答したケースでも、「いつまでに、この方法で解決する」という回答でないことです。特に 「いつまでに・・・」がほとんどない、ということです。 このような回答がされるのは、私の経験では次のようなケースが多かったと記憶しています。 2.一応答えだけしておき誠意を見せ、後は何もせずに、ほおって置き・様子を見よう。そのうち騒がなく なる。という見通しに基づくような場合。 さて、以前、私が公開した1文書(「山階鳥類研究所に期待すること」)で、事実が見えずに、いい過ぎや、誤解があるのではないか、と心配していました。 私は山階のバンディング対策に不満はあれど、誤解があるということであるとすれば、まずいと思い、その文書を取り下げ、意見を述べるのを控え、山階の対策・自助努力に期待をしておりました。現在も期待はしています。 |
|||
| 2.改善した実績の広報はどこでやるの | |||
| さてそこで、2月以降山階は、具体的にどんな対策をとったのだろう。日本鳥類研究機関のトップであるから問題を解決した実績を、公式に発表していないか、どこかに出ていなかいと、山階のホームページを探してみました。何故かどこにも出ていません。 まだ、対策は何も採られていないのかな。40年以上やってきたことの問題を解決するためには、また40年掛かるのかな?。まさかね、山階がそんなレベルとは思えない。 私が知る範囲で、山階が改善を行ったことといえば、標識調査の回収データーの登録・確認を取りいぞぎ実施し、あわせて、回収者にバンディングへの理解を一層深めようとしていることぐらいです。 これとて、2005年の私の回収報告2件についての、データー登録・確認・お礼の手紙を頂いたから、わかったことです。 その中で感じた改善点は、次の2点だと思います。 ・資料「渡り鳥と足輪」が白黒の文書であったのが、カラー印刷になったこと。 ・協力お礼の車用シールが、前回がノゴマ、今回はオナガガモになったこと。 また、遅れている、回収データーの登録を一生懸命データベースに登録して、今後に生かそうとしていることです。ただ、このことは私が回収連絡をしたために、わかったということで、他の人は知らないのです。 これでは、一生懸命改善されたとしても、身内の人や関係者以外は分からない。ということです。 改善したこと、改善中の内容をPRする方法、場所を確立しないと、何もしていないと誤解されます。 |
|||
| 3.良く分からないこと | |||
| 何もしていないため、あるいは対策や改善があまり進んでいないため、発表ができないのかなと。予想していたのですが、そうでもないようです。 例えば、MAKIさんのブログには、かすみ網の写真は駄目だとか、この表現は、私が言ったこととは違うと、具体的に反論が出ています。個々の問題に対応できるということは、それを全部集めれば、バンディング問題についての改善対策ができるということだと思います。 また、MAKIさんとのやり取りで理解できない、不思議なことも多いのです。 室長は、かすみ網に掛かった鳥の写真をホームページにのせたことについて、写真を取り下げるように言われたとのこと。 |
|||
| 4.取るに足らない問題 ? | |||
|
このように、バンディングを見学させて、意見を述べた結果をみて、内容が偏っている、と思えば、内容や意見の訂正を要求、修正意見を発表するということは当然の権利です。 見学した方が発表した意見について、その内容に誤記・誤解がある場合、当然訂正要求もするものです。一般的な訂正要求は、同一組織内、友人間では、口頭叉は文書で行われます。今回の場合、このケースでなく、「公」対個人(「山階」対MAKIさん)という組合せです。文書を送付して、訂正をさせるのではなく、山階のホームページで堂々と意見を述べられたほうが、あらゆる立場の人に知らしめるという意味で、価値があると思います。そうすれば、正式な山階鳥類研究所の見解であり、重みが増すと思うのですが。 尾崎室長とMAKIさんとは友人関係にあるのだろうか。そんなことはないと思うし、不思議で理解ができない対応である。このやり方の目的は何なんだろう。 よく考えてみると、佐藤さん、和田さん、MAKIさんと全て私信に対する回答、という形をとっている。もしかして、「バンディング問題」は山階にとって非公式な問題で、「 取るに足らない問題 ? 」なのであろうか。 |
|||
| 5.バンディングについて理解できないことと疑問 | |||
| 山階はバンディングについて、次のように説明している。 鳥類の渡り経路を知るほか、生息数のモニタリングにも役立つ調査研究で、繁殖・中継・越冬地の環境保護にも役立つ。 また、鳥類の寿命をはじめとして、種の識別・年齢・性別等観察では確認できないことでも、標識調査で初めて確認できます。これらのデーターは鳥類の基礎資料になります。 標識調査データは環境モニタリングへの利用もできるのです。山階では、標識調査は渡り鳥の渡り調査に、貢献している重要な方法としている。何を持って貢献しているといっているのか、について見解が分かれ理解しにくい部分である。 分かりやすい事例として、足輪をつけたツバメが東南アジアで見つかったから貢献しているとPRしているようだ。山階が「標識調査は渡り鳥の調査に貢献している」とここまで言うのは、環境省の補助金が出されている委託費の内容のためだろうと予想している。環境省の「公益法人に対する補助金・委託費等の一覧」によると 契約は、随意契約方式で、当該契約方式の理由、法人選定理由は専門研究機関として、他の追従を許さない。補助金名称は「鳥類観測ステーションの運営」。事業目的は鳥類の保護施策および国際協力の推進。具体的な内容は鳥類の標識調査を通して鳥類の渡りの状況生態等を解明する。ということになる。この内容と山階の説明することが当然一致している。われわれが、あれほど渡りの調査に貢献していない標識調査といっても、山階が、効果があるのだと言い切るのは、この事業委託費を受けているためと思われる。 要は、成果を何をもって評価するか、ということに立場と考え方の差があると思う。 |
|||
| 6.やってもらいたいバンディングもある. | |||
| このように考えていくと、標識調査はあまり価値がなく実施する意味がない、廃止した方が良いということになりかねない。いわゆる、バンディング全廃論である。 しかし、よく考えると次のような調査でのバンディングの有効性は証明されている。 発信機を付ける以前のアホウドリの固体識別調査。大型鳥類の足輪等がそれだと思う。 また、特定の小型の鳥種の固体識別調査には切札的な技術でもある。例えば、ブッポウソウ、保護対策を立てるための固体識別に必要な技術であると思うが。 実際に保護活動・基礎調査をするなら、足輪によるバンディングをして確認しないと、保護対策も実際には立てられない。と思う。保護対策を立てるため、野鳥の絶滅を防止するため等の必要性からを判断して、必要性があるなら、実施すべきという意味である。 もちろん、むやみやたらに、単なる研究心のためにバンディングをすべきではないと思う。 ここで私の言っているバンディングは、現在の鳥類観測ステーションで実施されているバンディングでなく、特定地域・特定個体群での保護対策のための特定のバンディングである。 |
|||
| 2006年8月4日 | |||
戻る TOPに戻る
私のバンディング問題 バンディング問題TOP